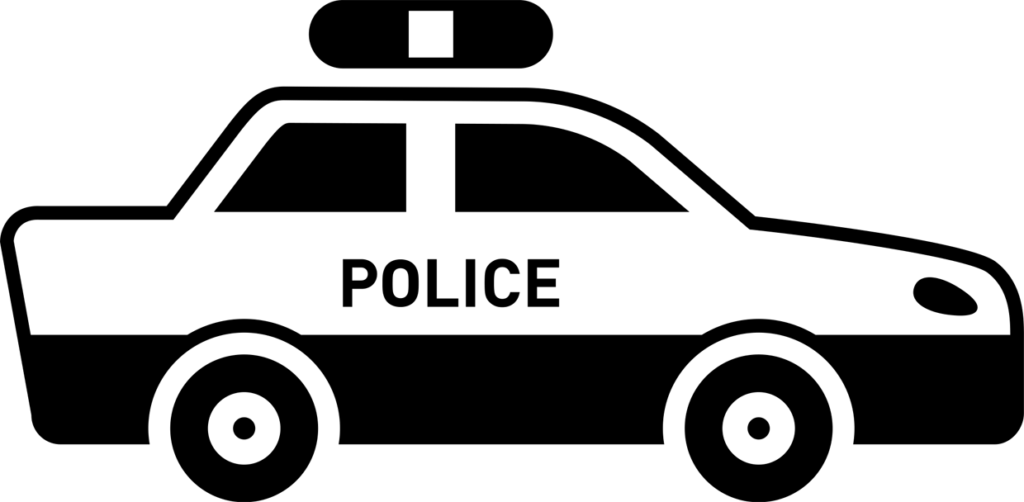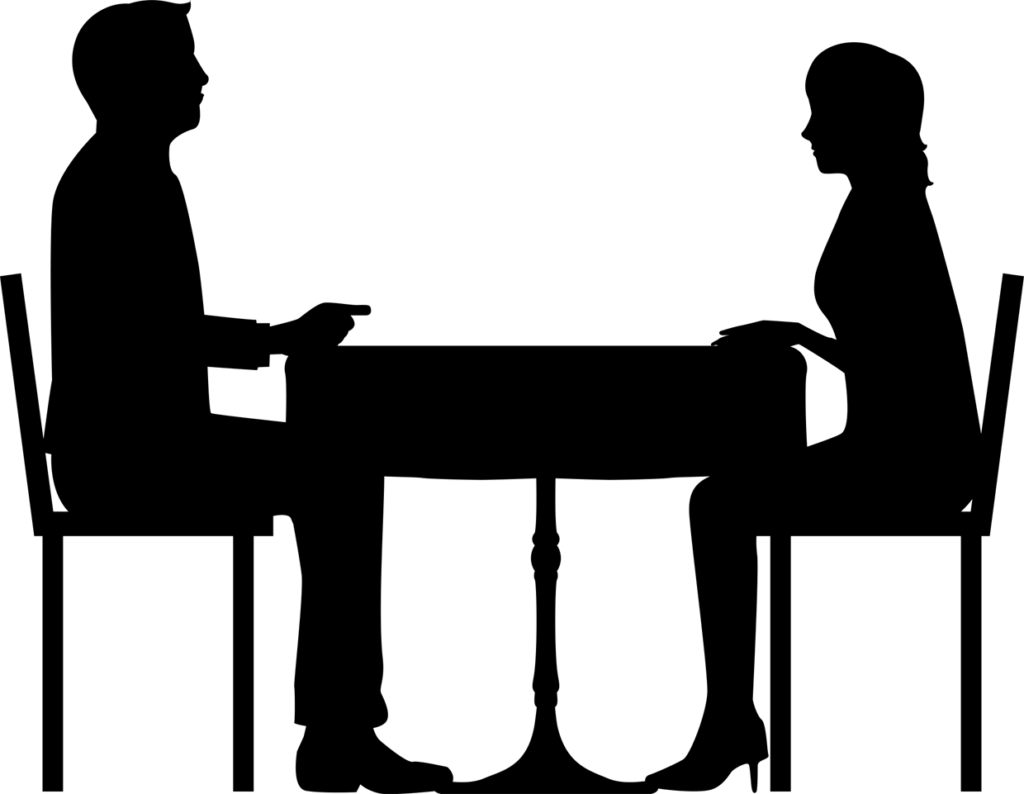親族の方が亡くなって相続が発生すると、相続人の方は財産だけでなく債務(借金)も引き継ぐことになります。
相続放棄
相続財産よりも債務の方が明らかに多いとき、相続人は相続放棄をすることができます。相続人が相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされます(民法939条)。相続人は財産も一切もらえない代わりに、債務(借金)も引き継ぐ必要がなくなります。
ところが、亡くなった方にどの程度の債務があるか、ということは、はっきりと分からないことも多く、相続放棄をすべきかどうか悩ましいケースがあります。
限定承認
こうしたときのために、民法には限定承認という制度も定められています(民法922条)。
限定承認をすると、相続人は、相続によって得た相続財産の限度でのみ被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。つまり、債務を弁済して相続財産が残れば、残ったものをもらえます。逆に、債務を全額弁済するだけの相続財産がなければ、相続財産がある分だけ弁済すれば済みます。
これだけ見ると、「いいとこ取り」の素晴らしい制度のように思えます。私も、大学に入って民法の勉強をした頃は、こんな素晴らしい制度があるのだから、誰もが相続放棄なんてせずに限定承認をするのではか、とまで思っていました。
限定承認があまり使われない理由
しかし、現実には、限定承認はほとんど使われていません。日本では毎年140万人程度の方が亡くなりますが、限定承認の手続は年に数百件(近年は700件前後)程度です。
限定承認が使われない理由として、手続きに手間、費用及び時間がかかることが挙げられます。限定承認の手続きを行うには、申立人(相続人)が被相続人の資産を詳しく調査し、裁判所に詳細な報告書を提出する必要があります。また、手間をかけて債権者への支払も行う必要があります。さらに、税務上の手続きが非常に煩雑になることもあります。
そして、多大な時間と費用をかけて限定承認手続をした結果、1円ももらえないという結果になることもあるのです。
このように、限定承認は一見すると「いいとこ取り」の便利な制度のように見えても、実際には使える場面が限られます。
専門家に相談
相続放棄は、一般市民にも広く知られている制度です。しかし、法律の字面だけを見ても分からないことも多々存在します。
例えば、限定承認や相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述をする必要があります(ここまでは民法に書いてあります)。ところが、3か月を過ぎてから多額の借金の存在が判明するようなケースもあります。法律の文面からは、こうしたケースではもはや相続放棄はできないようにも読めます。実際には、このような場合も家庭裁判所が相続放棄の申述を受け付けることも多いのです。
相続が発生して、相続放棄や限定承認を検討したいという場合は、なるべく早く弁護士に相談していただければと思います。