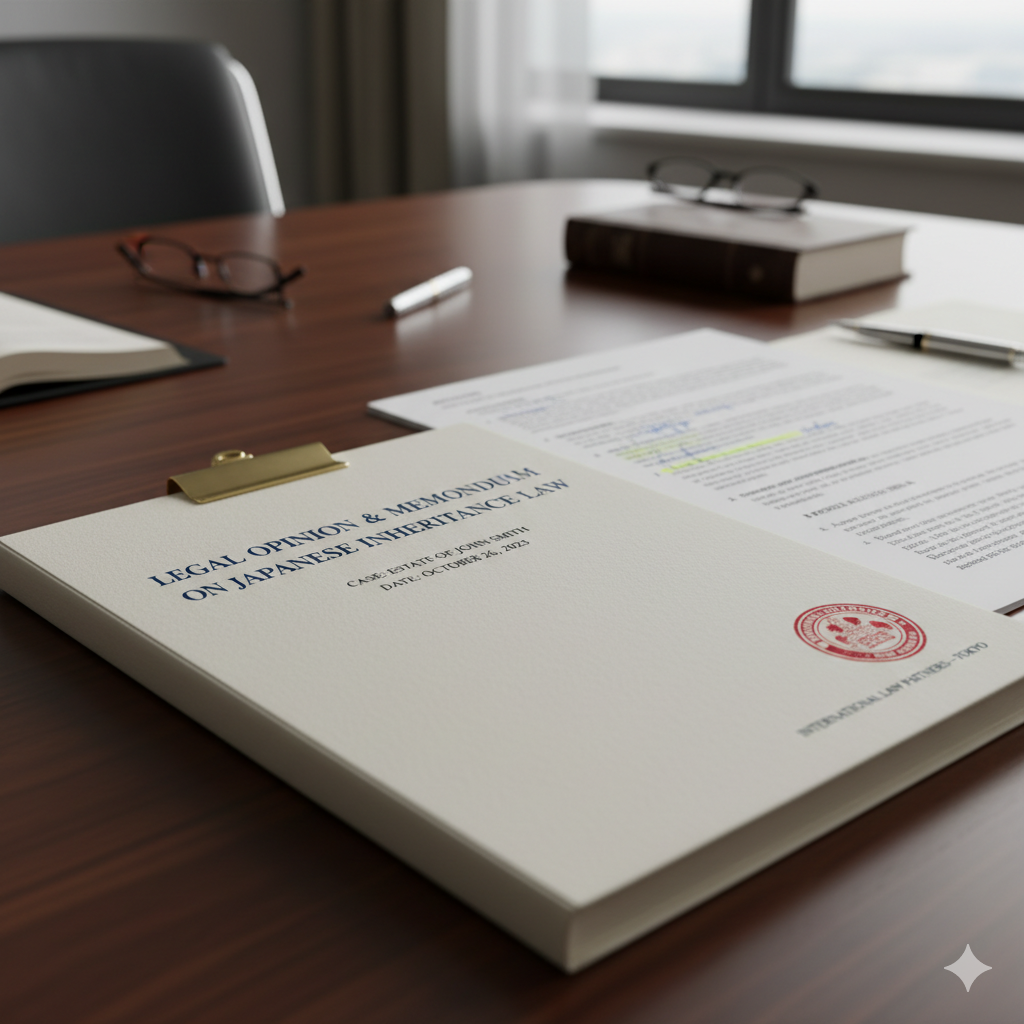アメリカに不動産や銀行口座などの遺産(プロベート資産)が残された場合、原則として現地の裁判所の監督下で行われる「プロベート(Probate)」という相続手続を経る必要があります。
この手続は、日本の相続手続とは大きく異なり、専門的な知識と多大な労力、そして特有のリスクを伴います。
1. 複雑なコミュニケーション:二者との膨大な英語でのやり取り
日本の相続人がアメリカのプロベート手続を進める場合、主に以下の二者と緊密に連絡を取り合う必要があります。
- 現地の弁護士:プロベート手続の申立代理を依頼する、現地の法律専門家。
- 財産管理者:裁判所によって選任され、遺産の管理・分配を行う責任者。日本の「相続財産清算人」に近い役割を担います。
これら関係者とのやり取りは、日本語で対応できる代理人を見つけない限りは、すべて英語で行われます。手続が複雑な場合や、日本の民法、戸籍制度、複雑な相続関係の説明が求められる場合などは、数百通に及ぶ英語のメールや書簡のやり取りが発生することも珍しくありません。
2. 相続制度の違い:日本民法の英文報告書が必要なケースも
アメリカ(各州)と日本では、相続に関する法制度(準拠法、相続人の範囲、相続分、戸籍制度など)が異なります。
そのため、プロベート手続の過程で、アメリカの裁判所や現地の弁護士から、「日本の民法ではこの場合どう解釈されるのか?」といった点について、弁護士による英文での報告書や意見書の提出を求められることがあります。
これには、日本の法律に関する正確な知識と、それを法的に適切な英語で説明する能力の両方が必要とされます。
3. プロベート手続に潜むリスク:相続できない可能性
プロベート手続では、債権者や他の相続人に名乗り出る機会を与えるため、手続の開始が公告されます。
この公告により、当初は把握していなかった事態が発生することがあります。
- 未知の相続人の出現: 被相続人(亡くなった方)の「最近親者(Next of kin)」として、申立人が全く知らなかった「子」などが名乗り出てくるケース。
- 新たな遺言書の発見: 申立人が把握していた遺言書よりも新しい日付の、あるいは内容が不利な遺言書が提出されるケース。
これらの結果、相続権の順位や相続分が変わり、多大な時間と費用、労力をかけてプロベート手続を進めたにもかかわらず、最終的に申立人が遺産を相続できないというリスクも存在します。
まとめ:米国プロベートは専門家へのご相談を
当事務所では、米国の相続案件(プロベート)に関する経験に基づき、現地の弁護士と緊密に連携を取りながら、煩雑な英語でのコミュニケーションや法制度の違いから生じる課題をクリアし、ご依頼者をサポートします。